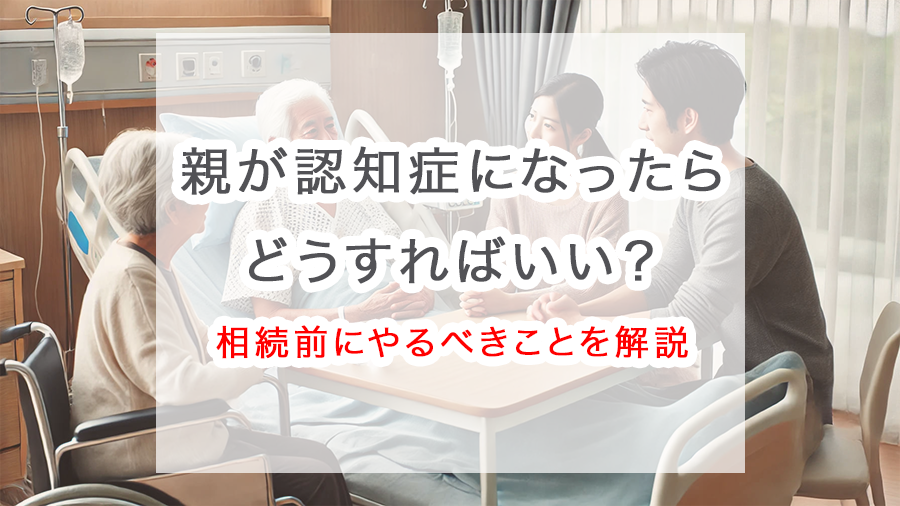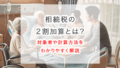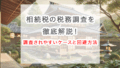親が突然、認知症になった場合、不安になる方も多いと思います。
当記事では、家族として相続を前に、どのように対応すればよいのかについて、詳しく解説していきます。
認知症に関する基本的な知識や、親が認知症になった際にどこに相談すべきかといった基本情報に加え、財産管理や相続に関わる法的な制度についてもわかりやすく紹介します。
認知症とは?
認知症とは、脳の神経が正常に働かなくなったり、神経細胞が減少したりすることで認知機能が低下し、日常生活に6か月以上支障をきたす状態を指します。日本では、高齢者の増加に伴い、認知症患者の数も増加しています。2022年の認知症患者数は約443万人、つまり高齢者の約8人に1人の割合になっています(厚生労働省報告)。
認知症の主な初期症状には以下のようなものがあります。
- ひどい物忘れ
- 日付や自分の年齢がわからなくなる
- 通い慣れた道で迷う
- 怒りっぽくなる・・・
親が認知症になった場合の4つのリスク
親が認知症になると、以下の4つのリスクが生じます。
事故や行方不明のリスク
認知症により、交通ルールが理解できなくなると、信号無視や横断歩道でない場所を渡るなど、事故に遭う危険が増します。また、自分がどこにいるかわからなくなり、迷子になって家に戻れなくなることや、徘徊によって行方不明になる可能性もあります。行方不明となり長時間外にいると、低体温症や脱水症状など、命に関わる事態になることもあります。
財産管理ができなくなるリスク
認知症になると、判断力が低下し、財産の管理が難しくなります。必要のないものを大量に購入したり、悪徳業者と契約してしまったり、詐欺に遭いやすくなります。銀行での出入金や振り込みもできなくなり、財産を正しく管理することが困難になります。
偏食による生活習慣病のリスク
認知症が進行すると、食事に関する問題が発生しやすくなります。例えば、食べたことを忘れて何度も食事をしたり、好きなものばかり食べたりするなど、栄養バランスが崩れがちです。その結果、糖尿病や高血圧、心疾患、脂質異常症などの生活習慣病のリスクが高まります。
家族も資産管理ができなくなるリスク
認知症が進行して親の判断能力が失われると、法律上、家族でも親の資産を管理することが難しくなります。銀行口座の凍結や、不動産の売却ができなくなる場合もあり、親の資産を介護費用などに活用することができなくなる可能性があります。
親に認知症の疑いが出たらやるべきこと
親に認知症の疑いがある場合、まずは認知症がどのような病気なのかを理解し、適切に対応するための準備をすることが重要です。認知症が進行する前に、対応策を講じておくことがリスクを避けるための第一歩となります。
認知症についての理解を深める
認知症になると、ささいなことで怒りっぽくなるなど、行動が変わることがあります。認知症の症状を知らずに、家族が不必要に冷たく接してしまうと、症状がさらに進行する可能性があります。家族で認知症に関する知識を共有し、対応方法を学ぶことが大切です。
地域の関係機関を把握・受診する
認知症かなと思ったら、まず地域の支援機関や医療機関に相談しましょう。地域包括支援センターは、認知症に関する情報提供や支援を行っており、社会福祉士や保健師などが相談に乗ってくれます。親が認知症の疑いがある場合は、まず地域包括支援センターに相談するのが良いでしょう。
早期の受診が大切
早期に受診を促すことが、認知症の進行を遅らせるために重要です。親が医療機関での診察を拒む場合は、「健康診断を受けよう」など、親の気持ちに寄り添ってやさしく勧めるようにしてください。
財産管理や相続について話し合う
認知症が進行すると、財産管理や相続の手続きができなくなるため、早めに対応しておくことが必要です。親の判断能力が残っているうちに、財産管理や相続について家族で話し合い、親の意思に基づいた取り決めをしておくことが重要です。
親に認知症の疑いがあるときに行うべき相続対策
親に認知症の疑いがある場合、早期の相続対策が重要です。認知症が進行すると、判断能力が失われるため、相続や財産管理の手続きが複雑になることがあります。ここでは、親が認知症になる前に行うべき6つの相続対策を紹介します。
遺言書
親がまだ判断能力を持っているうちに、遺言書を作成しておくことが大切です。遺言書を作成することで、親の意思に基づいた財産の分配が明確になり、相続トラブルを未然に防ぐことができます。遺言書には、財産をどのように分配するか、誰にどれだけ相続させたいかを具体的に記載します。
遺言書を作成する際には、いくつかの重要な条件を守る必要があります。まず、作成時には親が判断能力を有していることが必須です。特に自筆証書遺言の場合、遺言書には日付の記載、自筆での作成、署名および捺印が必要です。これらの条件が守られていない遺言書は無効とされ、相続手続きでトラブルになる可能性があります。
トラブルを防ぐためには、専門家の助言を受けて「公正証書遺言」を作成することをおすすめします。公正証書遺言は、公証人が遺言内容を確認し、法律に則って作成されるため、安心して相続手続きに備えることができます。また、遺言書の内容に相続人の「遺留分」を侵害しないよう配慮することも重要です。遺留分を無視した遺言書は後に争いの原因となりかねません。
生前贈与
親がまだ健康で、判断能力があるうちに、財産を家族に前もって贈与しておく「生前贈与」は有効な相続対策の一つです。例えば、自宅をあらかじめ子どもに贈与しておけば、親が施設に入所する際に資金が必要になった場合、子どもは自宅を売却してその資金を活用する選択肢を得ることができます。
ただし、年間110万円以上の贈与には贈与税が課せられるため、適切な税務対策が必要です。贈与税には控除や特例があり、これらを活用することで節税が可能ですが、申告手続きは複雑です。贈与税対策や適切な計画を立てるためには、税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
家族信託
「家族信託」は、親が判断能力を持っているうちに、信頼できる家族に財産管理を任せるための契約です。信託契約では、親が委任者として財産を信託し、受託者(通常は子どもなど)にその管理を任せます。この契約によって、親が認知症になった後でも、受託者が財産を管理し続けることができるため、安心して財産の運用を行うことができます。
家族信託は、親が預貯金や不動産の管理を子どもに任せたい場合に特に有効です。信託契約後、すぐに財産管理を移行することもできますし、親がまだ軽度の認知症の場合は、親自身が財産を使用することも可能です。信託契約を利用することで、財産管理がスムーズに行われ、親が判断能力を失った後も、財産が適切に運用されます。
委任契約
「委任契約」は、親が元気なうちに、財産管理を家族に代行してもらうための契約です。委任契約を結ぶことで、親が判断能力を失っていない段階で、家族が預貯金の管理や税金の支払い、不動産の売買などを代行できます。たとえば、親が所有するアパートの家賃管理を子どもに委任する場合、委任契約を結べば、手続きなしで管理を代行できるようになります。
委任契約は、親がまだ判断能力を保っているうちに結ばなければなりません。判断能力が失われた後に締結した契約は無効となるため、早めの対応が求められます。委任契約には、預貯金の管理や税金・保険の支払い、不動産売買契約、介護施設への入退所手続きなど、財産管理に加え幅広い内容を含めることができます。契約内容を公正証書で作成することも推奨されます。
成年後見制度(法定後見)
親がすでに判断能力を失ってしまった場合、成年後見制度を利用することも可能です。成年後見制度は、判断能力がない親の財産を保護するために、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や契約手続きを行う制度です。成年後見制度は、親の利益を守るために、財産の不正な使用や損失を防ぐ役割を果たします。
後見人には、親族だけでなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家が選任されることが多く、専門知識を持つ者が財産管理を担当するため、安心です。複数の後見人が選任される場合もあり、財産管理と身上監護を分担することもできます。
任意後見制度
「任意後見制度」は、親がまだ判断能力を持っているうちに、将来に備えて後見人を自分で選んでおく制度です。親自身が信頼できる人を後見人に指定し、契約を結んでおくことで、将来、親が判断能力を失った時に備えることができます。
任意後見制度の大きな特徴は、親自身が契約内容を自由に決められる点です。どこまで後見人に権限を与えるか、どのように財産管理をしてほしいかを事前に決めることができるため、親の希望通りの財産管理が可能になります。法定後見制度に比べて柔軟性が高く、親の意思を尊重した対応ができるのが利点です。契約を公正証書で作成する必要があるため、専門家に相談しながら進めると安心です。
おわりに
親に認知症の兆候が見られたら、早めに地域包括支援センターや医療機関に相談し、早期に診断を受けることが重要です。
また、認知症が進行する前に、財産管理や相続について家族でしっかり話し合い、適切な法的手続きを進めることが大切です。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
遺言作成や相続税対策など、もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。