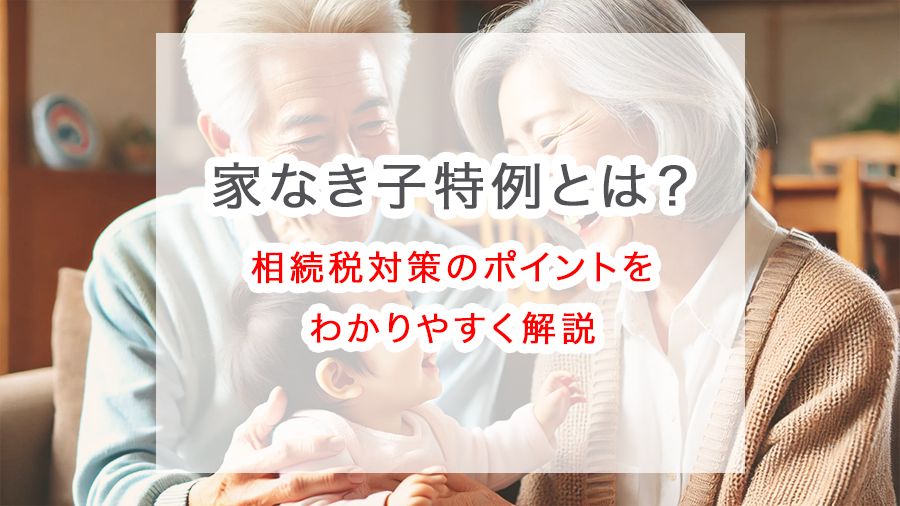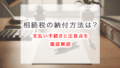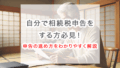相続税の負担を軽減できる「小規模宅地等の特例」は、同居している親族が利用するものと思われがちですが、一定の条件を満たせば、同居していない親族も適用可能です。
これが「家なき子特例」と呼ばれる制度です。本記事では、その制度内容や適用要件、適用可能なケース、申請の流れについて詳しく解説します。
1.家なき子特例とは?
「家なき子特例」とは、同居していない親族が宅地を相続した際に「小規模宅地等の特例」(土地の評価額を最大80%減額できる制度)を適用できる特例です。
「小規模宅地等の特例」は、被相続人(亡くなった方)が住んでいた宅地や事業用の土地を相続した場合に、相続税を大幅に軽減できる制度です。これにより、高額な相続税の負担で家を手放すことを防ぐほか、空き家問題の解消も目的とされています。
通常、この特例は配偶者や同居親族に適用されますが、一定の条件を満たせば、同居していない親族も対象となるのが「家なき子特例」です。
家なき子特例の適用要件4つ
家なき子特例を適用するには、4つの要件を満たす必要があります。
被相続人に配偶者や同居の相続人がいない
被相続人に配偶者(夫・妻)や同居している相続人がいないことが条件です。
死別・離婚・未婚などで配偶者がいない
相続人の誰とも一緒に住んでいない
例えば、父・母・子の3人家族で、父がすでに他界し、母が一人で住んでいたところ、母が亡くなった場合。子どもが別の都道府県で独立しているケースなどが該当します。
相続開始前3年間、一定条件下の持ち家に住んだことがない
相続人が相続開始前の3年間以上、一定条件下の持ち家に住んだことがないことが条件です。(賃貸物件に住んでいた場合など対象)
以下のいずれかの持ち家に居住していた場合、特例の対象外となります。
①相続人本人が所有する家
②相続人の配偶者が所有する家
③相続人の3親等以内の親族が所有する家
④相続人と特別の関係がある一定の法人が所有する家
例えば、夫名義のマイホームに住んでいる妻は②の基準に該当するため、家なき子特例を適用できません。一方で、いとこ(4親等以上)の持ち家に住んでいる場合は③に該当しないため、特例の適用が可能です。
相続開始後10か月間、その宅地を所有し続けている
相続開始(被相続人の死亡日)から相続税の申告期限(10か月以内)まで、その宅地を売却せずに所有している必要があります。
申告期限内に宅地を売却すると特例の対象外となる
申告期限後に売却すること自体に問題はないが、申告期限前に売買契約の手続きや登記変更を行うと、税務署に指摘される可能性があるため、慎重に対応する必要があります。
相続開始時に住んでいる家を過去に一度も所有したことがない
相続開始時に住んでいる家を過去に一度でも所有したことがある場合は、家なき子特例の適用を受けることができません。
この改正により、特例を目的とした意図的な住居の移動などが制限されることになりました。
家なき子特例が適用できる土地の面積
家なき子特例の適用要件を満たしていても、すべての土地が減額の対象となるわけではありません。適用できる土地の上限面積が決められています。
「被相続人が居住の用に供していた宅地等」の場合、特例の適用限度面積は330㎡までです。
例えば、500㎡の宅地を相続した場合:
330㎡までが減額対象(特例適用)
残りの170㎡は減額対象外
家なき子特例を適用した場合の減額計算
家なき子特例を利用すると、相続税額がどのように変わるのか、具体的な計算例を見てみましょう。
【家なき子特例が適用された場合】
土地の面積:300㎡
評価額:5,000万円
減額率:80%
計算式:
5,000万円 × 0.8(減額率)= 4,000万円の減額
5,000万円 - 4,000万円 = 1,000万円(特例適用後の評価額)
次に、相続税の基礎控除額を算出します。
基礎控除額の計算式:
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続人が子ども2人の場合:
3,000万円 +(600万円×2)= 4,200万円
課税価格の計算:
1,000万円 - 4,200万円 = 0円(非課税)
【家なき子特例が適用されなかった場合】
5,000万円 - 4,200万円 = 800万円(課税価格)
課税価格800万円 × 税率10% = 80万円の相続税が発生
このように、家なき子特例を適用すると相続税が非課税になる可能性があります。特に土地の評価額が高い場合、節税効果が大きくなるため、適用要件を正しく理解し、適切に活用することが重要です。
ケース別!家なき子特例を活用した相続税対策の考え方
家なき子特例を利用することで、どのような相続税対策が可能なのか、具体的なケースを見ながら確認していきましょう。
賃貸住宅に住みながら別荘や収益物件を所有しているケース
相続人が収益物件(賃貸住宅など)や別荘を所有していても、持ち家がなければ特例の対象になります。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 相続開始前3年間、所有する物件に居住していないこと
- 賃貸物件などに住んでいること
この仕組みを利用し、持ち家を貸し出して自分は賃貸物件に3年以上住むことで、相続時に節税できる可能性があります。ただし、節税目的が明確な場合、税務署に特例適用を認められないリスクもあるため、慎重に対策を進める必要があります。
相続開始後に持ち家を購入したケース
相続開始時に賃貸物件に住んでいたが、その後不動産を購入した場合、家なき子特例は適用されるのでしょうか?
持ち家の有無は、「相続開始前3年間」の状況で判断されます。そのため、
- 相続開始後に購入した場合は、家なき子特例の対象となる
- 相続後に相続した家に住み始めた場合も、特例の適用可
このように、相続開始後の住宅購入は特例適用に影響しないことがポイントです。
相続人には持ち家があるが、孫が「家なき子」に該当するケース
相続人(被相続人の子)が持ち家を所有している場合でも、その子(被相続人の孫)が「家なき子」に該当することがあります。
例えば、孫が
- 親の家を出て、3年以上賃貸物件に住んでいる
- 3親等内の親族(親やおじ)の持ち家に住んでいない
この場合、孫に不動産を「遺贈」することで特例を適用できます。ただし、
- 遺贈の場合、相続税は2割増しになる
- 孫を養子にすれば、相続税の基礎控除額が増えて節税効果が得られる
- 孫を養子にしても相続税は2割増しのまま
この方法は、相続税の基礎控除を増やす節税効果があるものの、税額の増加にもつながるため、慎重な検討が必要です。
相続後に宅地を賃貸物件にしたいケース
家なき子特例の適用要件には、「相続開始から10か月間、宅地を所有し続ける」という条件があります。これは一定期間の所有が求められるだけで、住む必要はないため、以下のような活用が可能です。
- リフォームや建て替えを行う
- 賃貸物件にして家賃収入を得る
ただし、相続税の申告期限前に売却すると特例の適用外となるため、売却は慎重に検討する必要があります。
「家なき子特例」申告の注意点
家なき子特例を適用するには、相続税の申告が必須です。申告の際には、通常の小規模宅地等の特例よりも多くの書類が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
非課税でも相続税の申告は必要
家なき子特例の適用を受けるためには、必ず相続税の申告を行う必要があります。要件を満たしていたとしても、申告をしなければ特例の適用は受けられません。
同居親族の場合より必要書類が多い
家なき子特例は小規模宅地等の特例の一種ですが、同居親族が適用を受ける場合と比べて、申請時に必要な書類が多くなります。
必要な添付書類
- 戸籍の附票の写しやマイナンバーカード
- 相続開始前3年間、相続人やその配偶者、3親等以内の親族、特別な関係がある法人が所有する住宅に住んでいなかったことを証明するための書類
- 相続開始時に住んでいた家を過去に所有していなかったことを証明する書類
おわりに
家なき子特例の適用可否について適用できるのか、どのようにすれば適用可能になるのか、判断が難しいこともあるでしょう。
不動産の評価は金額的に多額になるケースが多く、評価が複雑で、税理士によっても結果が異なることがあります。正しく節税し、適切に納税するためには、相続に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。