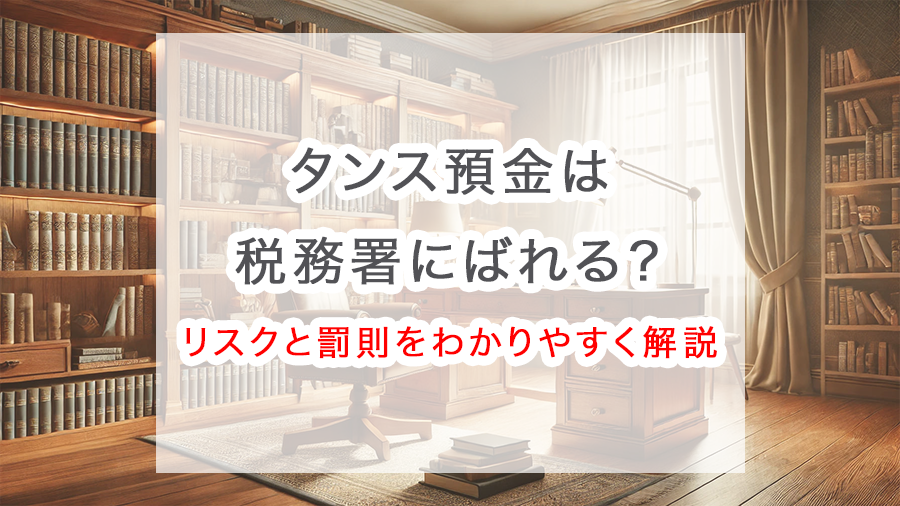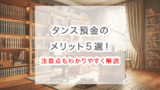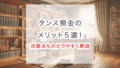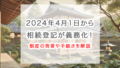「自分が死んだら、息子が多額の遺産を相続することになる。今のうちに相続税を避けるためタンス預金を考えているが、税務署にばれないか心配……」
このように考えている方もいるかもしれません。
結論としては、脱税目的のタンス預金は税務署にばれる可能性が高いため、絶対にやめましょう。なぜなら、発覚した場合には厳しい罰則が科されることがあり、最悪の場合は刑事罰として懲役刑を受ける可能性もあるためです。
この記事では、タンス預金が税務署に知られる理由や、発覚時に生じる税金面での罰則などタンス預金のデメリットについて詳しく解説します。
タンス預金が税務調査で発覚する理由
税務署は相続税の調査を行う際、さまざまな手段を用いてタンス預金の有無を確認します。
相続人の口座も調査対象となる
税務署は強い調査権限を持っており、相続税の税務調査では被相続人だけでなく相続人の口座も対象となります。
例えば、遺品整理中に300万円の現金が見つかり、相続人がそれを自分の口座に預けた場合、税務署は金融機関に照会をかけ、預金の動きを確認します。高額な入金があれば、その資金の出どころを調査し、脱税の可能性があると判断されることがあります。
税務署の主な調査手法は以下のとおりです。
①ヒアリング
相続税の税務調査では、相続人や関係者に対して次のような質問が行われます。
・被相続人の財産形成の経緯
・生前の生活費や趣味
・過去の贈与履歴
・配偶者の証券口座の有無や、相続開始直前の現金の使い道
・子供の収入、財産の受け取り状況、学歴など
これらの質問により、未申告の財産がないかを確認します。税務調査を受ける際は、事実を正直に答え、虚偽の説明をしないことが重要です。
②反面調査
税務署は、銀行や保険会社などに対して、被相続人の口座や取引履歴を確認することができます。また、生前に親しくしていた知人や関係者への聞き取り調査が行われることもあります。金融機関には情報開示を拒否する権利がなく、税務署の求めに応じる必要があります。
③実地調査
相続税の実地調査は、被相続人が生前に住んでいた自宅で行われることが一般的です。タンスや押入れ、金庫のほか、床下や仏壇、ベッド下などに現金が隠されていないかを確認します。また、室内にある高価な美術品や貴金属についても、申告の有無をチェックされます。
調査が行われる際は税務署から事前に日程調整の連絡があります。相続人全員が立ち会う必要はありませんが、できる限り立ち会うほうが望ましいでしょう。
口座の過去の出金履歴を調査できる
税務署は、相続税の調査の際に過去の口座の出金履歴をさかのぼって確認することができます。仮に何十年も前に被相続人が現金を引き出していた場合でも、その使用目的が明確でない場合、隠し財産として疑われる可能性があります。
特に100万円以上の大口出金は注意が必要です。出金した資金の使途を証明できなければ、タンス預金の疑いが生じ、場合によっては税務署が実地調査を実施する可能性があります。
税務調査が行われるタイミングは申告後1〜2年以内
税務調査は、相続税の申告後1〜2年以内に実施されることが一般的です。
税務調査が行われる確率は全体の1割弱とされていますが、納税額が多いケースでは調査の対象となる可能性が高くなります。調査を受けた場合、8割以上の人が何らか指摘を受け、追加の納税することになります。
申告から2年を経過すると、税務調査のリスクは大幅に低下します。また、相続税の申告期限から5年が経過すれば、特別な不正行為がない限り、税務署の徴収権が時効により消滅するため、調査が行われることはなくなります。
タンス預金が発覚した場合のペナルティ
相続税の課税対象となるタンス預金を申告しなかった場合、追徴課税が発生し、悪質なケースでは懲役刑や罰金が科される可能性もあります。
追徴課税の発生
タンス預金が発覚すると、加算税や延滞税による追徴課税が課されます。
【加算税】
適切に申告しなかった場合に科される罰則的な税金
【延滞税】
期限内に納付しなかった場合に発生する利息的な税金
期限内に申告しなかった場合は加算税と延滞税の両方が発生します。申告はしたものの納付が遅れた場合には、延滞税のみが課されます。
①加算税(罰則的な税金)
加算税には以下の3種類があります。
・無申告加算税(申告期限までに申告しなかった場合)
税額50万円以下の部分:15%
50万円超の部分:20%
・過少申告加算税(申告額が過少だった場合)
新たに納める税額50万円以下の部分:10%
50万円超の部分:15%
・重加算税(財産を隠蔽・仮装した場合)
無申告の場合:40%
過少申告の場合:35%
②延滞税(利息的な税金)
延滞税は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて発生します。税率は、市中金利の影響を受け、納付期限から2か月以内とそれ以降で異なります。
・2か月以内:最大7.3%
・2か月超過:最大14.6%
懲役刑や罰金の可能性
悪質な相続税の未申告や脱税が認められた場合、刑事罰の対象となることがあります。
①脱税犯(偽装や不正な手段で相続税を免れた場合)
10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(併科されることもある)
免れた税額が1,000万円を超える場合、その額に相当する罰金が科されることもある
②ほ脱犯(意図的に申告書を提出しなかった場合)
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
免れた税額が500万円を超える場合、その額に相当する罰金が科される可能性
③無申告犯(正当な理由なく申告書を提出しなかった場合)
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(情状により免除される場合もある)
このように、タンス預金の未申告は重大なペナルティを伴うため、適切な相続税の申告を行うことが重要です。
タンス預金のメリット、デメリット
タンス預金のメリット、デメリットはこちらの記事を参考にしてください。
おわりに
税務署は強い調査権限を持っており、タンス預金が発覚する可能性は高いです。
タンス預金は本来相続税の課税対象であり、適切に申告しなければなりません。正しく申告し、期限内に税金を納付することが、自身の財産を守る最善の方法です。また、税務調査の不安を抱えながら生活するよりも、法に則った適正な手続きを行うほうが安心して過ごせるでしょう。
結論として、相続税を逃れるためのタンス預金は避けましょう!
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税対策や遺言書の作成など、もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。