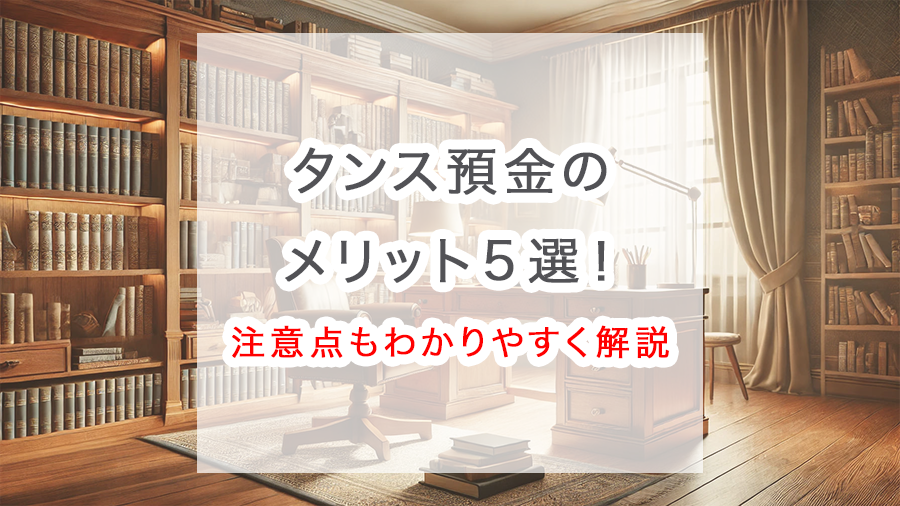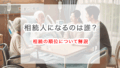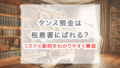「最近、タンス預金をする人が多いと聞くけれど、銀行の金利が低いなら自分もやってみようかな…」と考えていませんか?
確かに、タンス預金にはいくつかのメリットがあります。特に「非常時に現金がすぐ使える」ことは大きな利点です。しかし、一方で相続時の課税リスクや盗難の危険性など、デメリットも無視できません。
特に相続税対策としてタンス預金を利用することは適切ではなく、場合によっては追加で課税されるリスクもあります。
本記事では、タンス預金のメリット・デメリットを詳しく解説し、タンス預金をするべきかどうか解説します。
タンス預金のメリット5つ
いつでも自由にお金が使える
タンス預金なら、銀行の営業時間を気にせず、必要なときにすぐ現金を使えるというメリットがあります。
- ATM利用手数料がかからない
- 緊急時(ケガや病気など)にすぐ現金を用意できる
- 銀行に行かなくても支払いができる
例えば、家族が突然入院した際も、手元にまとまった現金があれば、手術費や入院費をすぐに支払えるので安心です。
銀行破綻のリスクから資産を守れる
銀行には「ペイオフ制度」があり、預金1,000万円までは保証されますが、それ以上の金額は保証されない可能性があります。
- タンス預金にすれば、銀行破綻による預金の損失リスクを回避できる
- 1,000万円を超える資産を持つ場合、タンス預金で一部を保管するのも選択肢の一つ
ただし、複数の銀行に分散預金すれば、1,000万円の保証を複数確保できるため、必ずしもタンス預金が最善の方法とは限りません。
相続時に口座凍結されても現金を使える
相続が発生すると、被相続人の銀行口座は凍結され、遺産分割協議が終わるまで引き出しができなくなります。
- 葬儀費用や当面の生活費をすぐに用意できる
- 口座凍結による資金不足を防げる
家族が亡くなった直後は何かと現金が必要になるため、手元にまとまったお金があると安心です。
国に資産を把握されにくい
現在、銀行口座とマイナンバーを紐づける制度が進められています。
タンス預金ならマイナンバーと紐づかず、資産状況を国に知られることがない
個人のプライバシーを守りたい人にとってメリットがある
家族に知られずに貯蓄ができる
タンス預金は、家族に知られることなく貯蓄できるため、自由に使える自己資金を確保する手段になります。
- 銀行預金や投資資産と異なり、記録が残らない
- 「へそくり」として、自分だけの資産を持つことができる
タンス預金にはこれらのメリットがありますが、リスクも存在します。次の章では、タンス預金のデメリットについて解説します。
タンス預金のデメリット4つ
タンス預金にはメリットがある一方で、さまざまなリスクが伴います。特に、資産管理や相続の面で問題が発生しやすいため、慎重に判断することが重要です。
盗難にあうリスクがある
タンス預金は空き巣や強盗の標的になりやすいという問題があります。
- 現金は持ち去られやすく、盗難のリスクが高い
- 現金の存在を知られていると、強盗に襲われる危険もある
もしタンス預金をする場合は、運び出しにくい重量のある金庫を使用するなど、防犯対策が必要になります。
紛失のリスクがある
長期間タンス預金を続けていると、自分でも保管場所を忘れてしまう可能性があります。
- 置き場所を忘れ、誤って処分してしまうことがある
- 家族にも秘密にしていた場合、本人が亡くなると遺族が現金の存在に気付かない
例えば、遺品整理の際に現金が隠されていたことに気づかず、タンスごと処分してしまうケースもあります。
災害で消失するリスクがある
タンス預金は火災・地震・洪水などの災害により消失するリスクがあります。
- 火災や洪水で現金が燃えたり流されたりすると、補償されない
- 火災保険や地震保険では現金は補償の対象外
- 銀行預金なら、通帳が焼失しても再発行可能
銀行に預けておけば、たとえ自宅が災害にあっても預金は保護されるため、リスク回避の手段として有効です。
遺産相続トラブルの原因になる
タンス預金は相続時にトラブルの火種になりやすいため注意が必要です。
- 存在を証明する証拠がないため、他の相続人が無断で持ち去るリスク
- 「そんな現金はもともとなかった」と主張されると、他の相続人は追及できない
また、遺産分割協議が終わった後にタンス預金が見つかると、遺産分割のやり直しや相続税の修正申告が必要になる場合もあります。
タンス預金は「家族に知られず貯蓄できる」というメリットがありますが、相続の際には大きな問題を引き起こす可能性があります。資産管理の面でもリスクを理解したうえで、慎重に検討することが大切です。
タンス預金は相続税対策にならない
タンス預金は相続税の課税対象であり、相続時には正しく申告しなければなりません。
仮に、相続税対策としてタンス預金の存在を税務署に隠したとしても、税務調査で発覚する可能性が高く、発覚した場合には重加算税や延滞税が課せられるため、大きなリスクを伴います。
税務署はどのようにタンス預金の存在を把握するのでしょうか?以下の方法で徹底的に調査を行います。
被相続人だけでなく家族の口座も調査される
税務署は、被相続人の金融資産を調べるために、銀行や証券会社へ照会をかけ、口座の出入金履歴や残高証明を確認します。
- 被相続人の口座だけでなく、家族の口座もチェック対象となる
- タンス預金を相続税逃れのために家族の口座へ移した場合も発覚する
つまり、被相続人が生前にタンス預金を隠し、相続税を回避しようと家族の口座に預けても、税務署の調査でばれる可能性が高いということです。
口座の過去の出金履歴をさかのぼって調査
税務署は、過去何年にもわたる口座の出金履歴を調査します。
- 何十年も前の出金であっても、その使用目的を証明できなければ、隠し財産と見なされる可能性がある
- 特に100万円以上のまとまった出金は、タンス預金の疑いをかけられることが多い
もし、出金額の使い道を明確に説明できなかった場合、税務署が実地調査(家宅捜索)を実施することもあり、その結果タンス預金の存在が発覚するケースが多くあります。
【おすすめ】タンス預金をするなら数十万円程度に留めるのが無難
タンス預金は、日々の生活だけではなく、口座凍結時や災害時などの非常時には役立つため、少額の現金は手元に置いておいた方が良いでしょう。
必要以上の現金は金融機関へ預け、相続時は正しく申告を行いましょう。
おわりに
タンス預金には一定のメリットがありますが、大きなリスクを伴うため、適切に管理することが重要です。
タンス預金は、適切な範囲で活用し、必要以上の現金は金融機関に預けることで、リスクを回避しながら安心して資産を管理できるでしょう。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税対策や遺言書の作成など、もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。