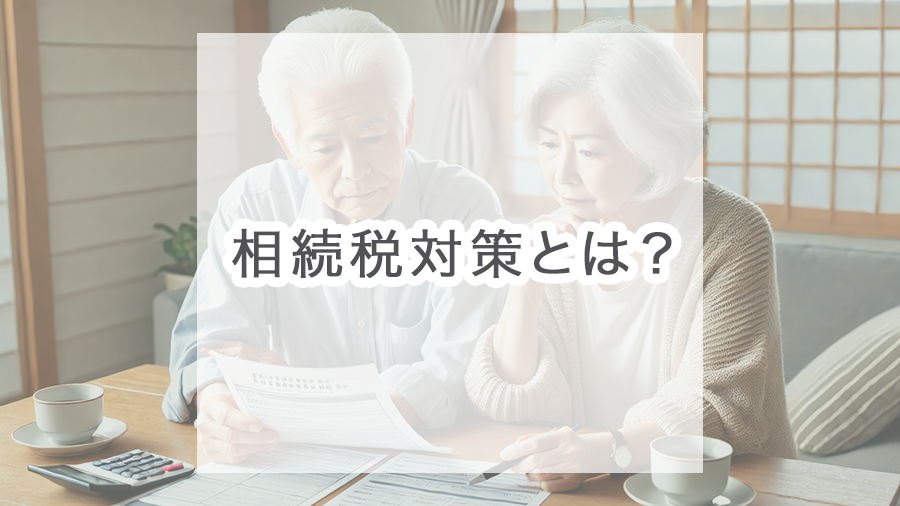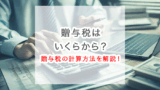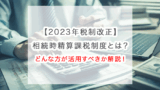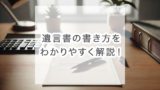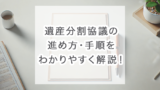「相続税対策って、何から始めればいいの?」
「節税したいけど、何に気を付ければいいの?」
相続税対策は、誰もが直面する可能性のある重要なテーマです。しかし、複雑な税制や専門用語が多く、何から手をつければいいか分からない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続税対策の基本から、具体的な節税方法、注意点までをわかりやすく解説します。
この記事を読んで、是非相続税対策を実施してみてください。
相続税とは?
相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した際に課税される税金です。
相続税の計算方法
相続税は、大まかに以下の手順で計算します。
- 相続財産の評価額を計算する
- 基礎控除額を差し引く
- 課税対象となる相続財産に税率をかける
- 税額控除を差し引く
そうぞくんでは相続税のシミュレーションを簡単に行うことができますので、まずはこちらで概算の相続税をご確認ください。

相続税の節税対策
相続税の節税対策は、生前贈与、不動産活用、生命保険活用など多岐にわたります。それぞれの方法を理解し、適切に組み合わせることで、相続税の負担を軽減できます。
生前贈与
生前に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。贈与税には年間110万円までの非課税枠や、特定の条件を満たす場合に利用できる特例があり、これらを活用することで効果的な節税が可能です。
暦年贈与
年間110万円までの贈与は贈与税が非課税となる制度です。毎年コツコツと贈与することで、将来の相続税を大幅に節税することができます。例えば、複数のお子様やお孫様に毎年贈与することで、相続財産を計画的に減少させることができるでしょう。ただし、贈与の記録をきちんと残しておくことが重要です。
相続時精算課税制度
2,500万円までの贈与は贈与税が非課税となる制度です。ただし、この制度を選択すると、贈与者が亡くなった際に贈与財産が贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税が計算されます(2024年1月からは、年間110万円の基礎控除あり)。将来的に相続税率が上昇すると予想される場合や、特定の財産を早期に移転したい場合に有効です。
詳細はこちらの記事を参考にしてください。
不動産を活用した節税
不動産は、相続税評価額が市場価格よりも低くなるため、相続税対策に有効です。特に、小規模宅地等の特例や貸家建付地の評価減を利用することで、大幅な節税が期待できます。
小規模宅地等の特例
自宅や事業用の宅地を相続する場合、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できる制度です。この特例は、被相続人と同居していた親族や、事業を承継する親族が利用できます。適用要件や計算が複雑ですが、そうぞくんでは自動で最も有利と考えられる評価を自動で計算することができます。
貸家建付地
所有する土地に賃貸住宅を建設することで、土地の評価額を減額できる制度です。賃貸住宅を建てることで、土地の評価額が貸家建付地として評価され、相続税評価額が減額されます。ただし、賃貸事業が適切に運営されている必要があります。
生命保険を活用した節税
生命保険の死亡保険金は、相続税の非課税枠が設けられているため、相続税対策に有効です。生命保険金を活用することで、相続税の納税資金を準備したり、特定の相続人に財産を承継させたりすることができます。
納税資金対策
相続税の納税資金を準備することは、相続税対策において非常に重要です。生命保険の活用や不動産の売却、延納・物納などを検討し、納税資金を確保しましょう。
納税資金の準備方法
生命保険の活用、不動産の売却、延納・物納など、様々な方法で納税資金を準備できます。生命保険は、相続税の納税資金を準備する上で非常に有効な手段です。
納税資金対策のタイミングと注意点
納税資金対策は、早めに始めることが重要です。また、相続税の申告期限や納税期限に注意する必要があります。納税資金が不足する場合、延納や物納を検討することもできます。
「争続」対策

相続財産の分割方法や割合を明確にすることで、相続人間の争いを防ぐことができます。遺言書の作成や遺産分割協議、家族信託などを活用し、円満な相続を目指しましょう。
遺言書の作成
遺言書は、遺産分割の方法を指定することで、相続争いを防ぐための有効な手段です。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれの特徴を理解し、適切な遺言書を作成しましょう。
遺産分割協議
相続人全員で遺産分割について話し合い、合意することで、円満な相続を実現できます。遺産分割協議では、相続人全員が納得できる分割案を作成することが重要です。必要に応じて、弁護士などの専門家を交えて協議を進めましょう。
家族信託
財産の管理や処分を信頼できる家族に託すことで、相続争いを防ぐことができます。家族信託は、認知症などで財産管理が難しくなった場合に特に有効です。
相続税対策の注意点
相続税対策を行う際には、税務調査や税理士選びなど、注意すべき点がいくつかあります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めましょう。
税務調査
相続税の申告後、税務署による税務調査が行われることがあります。税務調査で申告漏れや不正が発覚すると、追徴課税や加算税が課される可能性があります。税務調査に備えて、日頃から適切な記録を残しておくことが重要です。
税理士選び
相続税対策は複雑で専門的な知識が必要となるため、税理士に相談することをおすすめします。税理士を選ぶ際は、相続税に関する専門知識や実績があるかを確認しましょう。
専門家への相談
相続税対策は、専門家の知識と経験が必要となる場面が多くあります。税理士、弁護士、不動産鑑定士など、それぞれの専門家の役割を理解し、必要に応じて相談しましょう。
専門家の役割と選び方
税理士、弁護士、司法書士、不動産鑑定士など、相続税対策に関する専門家は多岐にわたります。それぞれの専門家の役割を理解し、自分の状況に合った専門家を選びましょう。
相談の準備と注意点
専門家に相談する際は、相続財産の状況や家族構成など、事前に情報を整理しておきましょう。また、相談内容や費用についても事前に確認しておくことが重要です。
相続税対策のよくある質問
Q:相続税はいくらからかかりますか?
A:基礎控除額を超える相続財産がある場合に課税されます。
Q:相続税対策はいつから始めるべきですか?
A:早ければ早いほど効果的です。
Q:相続税対策にはどのような費用がかかりますか?
A:税理士報酬や不動産鑑定費用などがかかります。
まとめ
相続税対策は、早めの準備と専門家への相談が重要です。この記事を参考に、あなたも今日から相続税対策を始めてみてください。
「そうぞくん」は、相続税の申告書を簡単に作成できるWEBサービスです。相続税の節税対策について、もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。是非、ご利用ください。