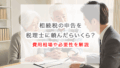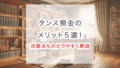これから遺言を作成するときや、親族が亡くなったときに、誰が相続人となるのかが問題となります。
誰が相続人となるかについては、法律(民法)で厳密なルールが決まっており、生存している親族が誰かによって相続の順位が存在し、その順位に定められた人が相続人となります。
このページでは相続人になるのは誰か、相続の順位を中心にお伝えします。
配偶者は常に相続人になる
まず、誰が相続人になるかについて、どのような家族構成でも、配偶者は常に相続人となることを知っておきましょう。
ここに言う配偶者とは、法律上の婚姻をした人の事をいい、婚姻届の提出をしていない事実婚・内縁にある人については、最高裁判例で含まないと判断されています。
相続の順位
次に、生存している親族が誰かによって、次の第1順位から第3順位の相続に分かれます。
第1順位 子
第2順位 親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
第1順位 子
子がいる場合には、第1順位として子が相続人となります。
子が亡くなっている場合でも、その子(被相続人からすると孫)も代襲相続で相続人となることができ、この相続の場合も第1順位として相続人となります。
そのため、子・その子(孫)・兄弟姉妹といる場合で、子が亡くなっている場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人になるのではなく、第1順位として孫が相続人になります
子であればすべて相続人となるので、例えば再婚した場合に前に結婚していたときに生まれた子や、女性で結婚して家を出た人でも、子として相続人になります。
また、養子縁組で迎えた子も相続人になります。
第2順位 親などの直系尊属
第1順位として相続する子がいない場合には、親などの直系尊属が相続人となります。
直系尊属とは、父母や祖父母など自分より前の世代に当たる、一直線につながる系統の親族のことをいいます。
子が亡くなった場合の相続のケースなので、現実には親か、あっても祖父母が限界でしょう。
第3順位 兄弟姉妹
第1順位として相続する人も、第2順位として相続する人もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の場合にも代襲相続が発生するのですが、兄弟姉妹の場合には代襲相続人が亡くなっている場合の再代襲相続ができないとされているので注意をしましょう。
相続人がいない場合
以上の相続人がいない場合には、民法に定められた手続きを経て、相続財産は国におさめられることになります。
なお、相続人がいない場合に限って、内縁の妻のような、生前に亡くなった人に貢献のあった人に対して財産を分け与える、特別縁故者への財産の分与という制度もあります。
注意が必要なケース
相続人となるかどうか注意が必要なケースをいくつか確認しましょう。
相続放棄では代襲相続は発生しない
先ほど第1順位の相続人である子、あるいは第3順位の兄弟姉妹について、代襲相続で相続人になる人がいることをご紹介しました。
代襲相続は相続欠格に該当したり相続人の廃除がされた場合でも発生します。
ただ、相続放棄をした場合には代襲相続は発生しないことを知っておきましょう。
つまり、子が相続放棄をした場合に、その孫は代襲相続をせず、相続人とはなりません。
相続放棄によって相続の順位がずれることがある
相続放棄をすると第1順位の相続が第2順位の相続・第3順位の相続と相続の順位がずれることがあります。
例えば、父・母・子1人の家庭で父が亡くなった場合に、子が相続放棄をしたとします。
相続放棄をした場合には、その子は最初から相続人ではなかったとして取り扱われるため、相続が始まった当初は第1順位だったものの、子がおらず第2順位・第3順位にずれることがあるのです。
相続放棄をする場合には、借金などの債務があることが多いため、次に相続人になる人がいる場合には連絡するなど対応を検討しましょう。
後から子が増えるケースがある
遺言で認知をしたり、死後に認知の訴訟を起こされたことで認知の効力が発生するなど、亡くなった後に、子が増えるケースがあります。
また、亡くなったときに、妻が妊娠をしていた場合、その子は生まれたときには相続人であるとみなすという規定があり、生まれた段階で相続人となる人が増えます。
このような場合には、子はいなくても親がいるので第2順位の相続であった場合でも、子が生まれて第1順位の相続になることもあります。
養子縁組の方式に注意
養子縁組には、①実親との関係が存続する普通養子縁組と、②実親との関係が終了する特別養子縁組の2種類があります。
①普通養子縁組をした子は、養子縁組後も相続人である子である一方、②特別養子縁組をした子は法律上子でなくなるため、相続人にはなりません。
養子縁組の方式によって結論が異なるので注意しましょう。
連絡がとれない相続人がいる
行方不明など連絡がとれなくなっている相続人がいる場合でも、法律上相続人である場合には、遺産分割で相続人として取り扱う必要があります。
後述する戸籍と住民票で探しても現在の居場所がわからない場合、状況に応じて不在者の財産管理人を選任する・失踪宣告を行うなどの対応が必要です。
相続人を確定する方法
被相続人が亡くなって相続が発生した場合には、法律上相続人を確定します。
まず、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せ、相続人となる人の戸籍謄本を取り寄せて、相続人関係を確定させます。
例えば、夫婦と子1人の場合でも、生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取り寄せることで、実は結婚が2度目で前婚で子をもうけているなどの事情がない、ということを確定することができます。
まとめ
このページでは、相続人になるのは誰なのか、相続の順位を中心にお伝えしました。
親族関係に応じて、相続人や相続分も変わってきます。
誰が相続人となるのか、法定相続分がどれくらいなのか、不明な点がある場合には専門家に相談することを検討しましょう。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。