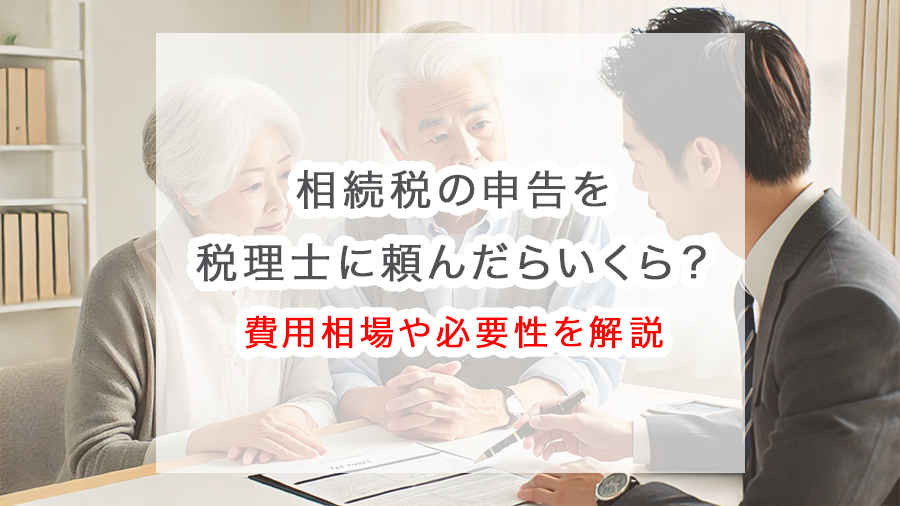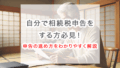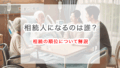親族が亡くなると相続が発生し、財産の総額によっては相続税がかかる場合があります。相続税は申告が必要な税金であり、自分で財産を評価し、計算・申告を行う必要があります。また、相続税は各相続人がそれぞれ納めるものです。
しかし、相続税の申告は複雑なため、多くの人が税理士に依頼しています。財務省の調査(令和4年度)によると、相続税申告の86%は税理士が関与しています。
では、税理士に依頼するといくらなのか。複数の相続人がいる場合、税理士費用は誰が負担するのでしょうか。本記事では、税理士費用の相場や負担者、税理士の必要性について詳しく解説します。
相続税申告を税理士に依頼した場合の費用相場
相続税申告にかかる税理士費用は、相続財産総額の0.5~1.5%が目安です。
例えば、相続財産が5,000万円の場合は25~75万円、1億円の場合は50~150万円ほどかかることが一般的です。相続財産が多いほど作業量が増えるため、税理士費用も高くなります。
税理士費用は基本報酬と加算報酬に分かれています。
- 基本報酬:税理士が設定している標準的な費用
- 加算報酬:特定の条件に該当する場合に追加される費用
加算報酬が発生する主なケースは以下のとおりです。
- 相続人の数が多い
- 評価が難しい財産がある(形状が特殊な土地、非上場株式など)
- 申告期限までの期間が短い
加算報酬の条件は税理士ごとに異なるため、依頼前に確認することをおすすめします。
相続税の税理士費用は誰が負担するのか?
相続税の申告を税理士に依頼する場合、その費用は特定の誰かが必ず負担しなければならないという決まりはありません。誰が支払っても問題なく、相続人同士の話し合いで決めることが一般的です。
多くの場合、相続人全員で費用を分担しますが、特定の相続人が全額負担することも可能です。負担の方法や割合については、遺産分割協議の中で決定されるケースが多くみられます。
税理士費用は相続税申告時に債務控除できる?
相続税の金額は、被相続人(故人)が残した遺産の総額によって決まります。相続税を計算する際には、「被相続人の借金」や「葬儀費用」などを遺産の総額から差し引くことができます。これを「債務控除」といい、控除を適用することで相続税の負担を軽減できます。
しかし、税理士費用は相続税法(相続税法基本通達)で定められた債務控除の対象には含まれていません。そのため、相続税申告の際に遺産総額から差し引くことはできません。
税理士費用を払って依頼する必要はあるのか?
令和4年度の財務省調査によると、相続税申告の86%は税理士が関与しています。自分で申告を済ませた人は14%以下です。
では、多くの人が税理士に依頼する理由は何でしょうか?
ここでは、税理士が必要とされる主な理由を説明します。
申告漏れによる損失を防ぐ
相続税の申告漏れには、以下の2つのパターンがあります。
- 申告したが、財産の記載漏れや誤りがあった
- 自分は相続税の対象外だと思い、申告しなかった
いずれのケースでも、期限を過ぎると追徴課税を受け、結果的に納税額が増えるリスクがあります。
財産評価の誤りで税金を払いすぎるリスク
相続税の金額は財産の評価額によって決まります。現金は分かりやすいですが、不動産や有価証券などは適切な評価が難しく、専門知識が必要な場合があります。
誤った評価をすると、相続税を払いすぎる可能性があります。税務署は納税不足の場合は指摘しますが、払いすぎても返金の通知はありません。そのため、知らないうちに余分に支払ってしまうことがあります。
控除や特例を活用できず損をする
相続税には、税負担を軽減する控除や特例があります。適用条件を満たせば、税額が大幅に減ることもありますが、計算が複雑で一般の人が理解するのは難しい場合があります。
適用できる控除を知らずに申告すると、本来支払う必要のない税金を余分に負担することになります。税理士に依頼すれば、適用可能な制度を適切に利用できます。
二次相続を考慮せず損をする
例えば、最初に父が亡くなり、次に母が亡くなると、母の相続は「二次相続」にあたります。
このとき、一次相続(父の相続)で適用できた配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などが、二次相続では使えなくなることがあります。
最初の相続で適切な分割をしないと、最終的な相続税負担が高額になることもあるため、税理士による長期的な視点でのアドバイスが重要です。
そうぞくんを使うと無料で申告書ができる
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。

もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
質問に答えるだけ
申告で漏れがないように、財産の洗い出しや控除や特例など質問に答えることで安心してご利用いただけます。
計算の自動化
解説に沿った金額を入力するだけで、自動で財産の評価をします。
また、小規模宅地等の特例はもっとも有利になるように自動計算し、評価金額を算出します。
困ったら専門家へ
専門家(税理士、弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士など)が登録されています。専門家のアドバイスが必要な場合、専門家を選んでチャットでご相談いただくことが可能です。
相続で税理士報酬以外にかかる費用
相続には税理士費用のほかにも、さまざまな費用が発生することがあります。主な費用について説明します。
弁護士報酬
相続では、遺産分割のトラブルや、特定の相続人による財産の使い込み、遺言の内容に関する争いが発生することがあります。こうした問題の解決を支援するのが弁護士です。
弁護士は、依頼者の代理人として遺産分割協議や相続人との交渉を行い、必要に応じて裁判を起こすこともあります。
遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議自体は相続人同士で自由に行えますが、法的に有効な遺産分割協議書を作成するには専門家に依頼することが一般的です。
- 税理士:相続税申告と遺産分割協議書の作成
- 弁護士:相続トラブルの解決と遺産分割協議書の作成
- 司法書士:不動産の名義変更と遺産分割協議書の作成
- 行政書士:遺産分割協議書の作成のみ
測量費用
相続財産に不動産が含まれる場合、土地の測量が必要になることがあります。特に、相続人が複数いて土地を分割相続する際には、分筆登記のために地積測量図を作成する必要があります。
測量は専門的な作業のため、測量士や土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。費用は、測量を必要とする相続人が負担することが多くなっています。
登記費用
相続した不動産の名義を変更する手続きは相続登記と呼ばれます。この際の費用として、司法書士への依頼費用や登録免許税が発生します。
- 司法書士報酬:不動産の名義変更の手続きを依頼する費用
- 登録免許税:不動産を相続した人が支払う税金
相続人ごとに別の税理士に依頼できる?
相続税の申告は相続人ごとに行うため、それぞれが異なる税理士に依頼することも可能です。ただし、費用を抑えるためには1人の税理士にまとめて依頼するのが一般的です。
多くの税理士事務所では、相続人が2人目以降の場合、基本報酬額の10%程度で対応してくれるため、費用負担を軽減できます。
ただし、
- 個別に信頼している税理士に依頼したい
- 相続人全員で同じ税理士に依頼するのが難しい
といった事情がある場合は、各自で別の税理士に依頼することも選択肢のひとつです。
おわりに:まずはそうぞくんを無料でお試しください
相続税申告は、自分で行うことも可能だが、多くの人が税理士に依頼しています。
資産が多額、未上場株式など評価が複雑な資産が含まれている場合は、税理士に依頼した方が望ましいケースはあります。この記事を参考に、自分に合った税理士を選ぶ際の参考にしてください。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税対策や遺言書の作成など、もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。