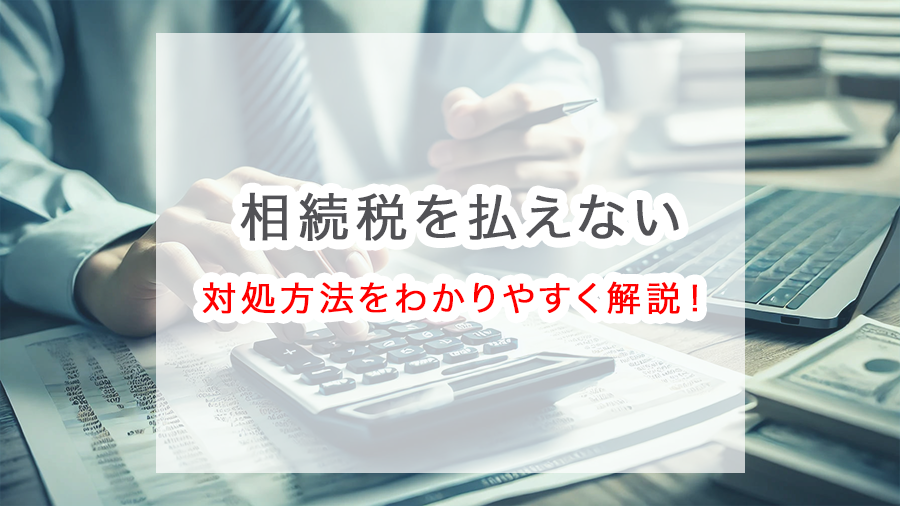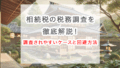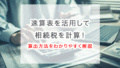相続税を期限内に申告しないと「無申告加算税」、期限内に納めないと「延滞税」がかかる可能性があります。
例えば、「相続税の金額がわからない」「手続きが難しくて放置している」といったケースでは、ペナルティとして両方が課される可能性があることになります。
対応が遅れるほど負担が増えるため、できるだけ早めに対処することが大切です。
この記事では、相続税を払えないときの対処法をわかりやすく解説していきます。
相続税が払えない場合の対応策
相続税の納付が難しいときは、次のような対応方法があります。
- 延納制度を利用する
- 物納制度を利用する
- 相続した不動産を売却する
- 金融機関から借り入れる
- 相続放棄を選択する
それぞれの方法について順に確認していきましょう。
延納制度の活用
相続税は本来、現金で一括納付が原則ですが、どうしても困難な場合は「延納制度」や「物納制度」の利用が検討できます。
延納制度は、相続税を分割で納められる制度で、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 相続税(または贈与税)の額が10万円を超えている
- 金銭による一括納付が困難な範囲に限られる
- 期限内に「延納申請書」と「担保関連書類」を提出する
- 担保の提供ができること
※ただし、税額が50万円未満かつ延納期間が3年以下なら担保は不要です
(出典:「相続税・贈与税の延納の手引」国税庁)
延納を選ぶと利子税が発生します。延納可能な年数や利率は、不動産などの割合に応じて変動し、基準利率が7.3%を下回る場合は、次の特例計算式が適用されます。
特例割合=年利率 × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%(※小数点第2位以下切り捨て)
※延納特例基準割合とは、前年11月末時点で財務大臣が告示した利率に0.5%を加えた数値です。
物納制度を活用する
物納制度は、現金での納税が困難な場合に、不動産などの資産で相続税を納めることができる制度です。
利用には以下の条件を満たす必要があり、物納を行っても利子税が課されることがあります。利子税の計算方法は、延納制度と同じです。
- 延納を利用しても金銭で納税が難しいと認められる範囲であること
- 物納に充てる財産が所定の種類・順序に該当していること
- 「物納申請書」と「関係書類」を期限までに提出すること
- 提出された財産が物納に適したものであること
(出典:「相続税の物納の手引(手続編)」国税庁)
なお、物納に使用できる財産には優先順位があり、指定された種類の財産に限定されています。詳細は国税庁の資料を確認してください。
物納はあくまで延納でも納付が難しい場合の最終手段として利用する制度であることを理解しておきましょう。
相続不動産の売却
相続した不動産を売却して相続税の納税資金を確保する方法もあります。
この場合は、まず相続登記(名義変更)を済ませておく必要があります。また、不動産を売却すると譲渡所得が発生し、所得税や住民税の課税対象になる可能性があるため注意しましょう。
相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却した場合は、「取得費加算の特例」により課税負担を軽減できる場合もあります。
(参考:「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」国税庁)
金融機関からの借入れ
不動産がすぐに売却できない場合、金融機関から借入れを検討する方法もあります。
相続した不動産を担保にして資金を借りることができるケースもありますが、担保として利用するには相続登記が完了している必要があります。
登記が未了の場合は借入れができない可能性があるため、事前に確認しておきましょう。
相続放棄の選択
相続財産に多額の借金や負債が含まれているときは、相続放棄を検討する価値があります。
相続放棄とは、相続に関するすべての権利を放棄する手続きで、これにより相続税の納税義務もなくなり、マイナスの財産を引き継ぐことも避けられます。
ただし、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。相続放棄が適切かどうかは状況により異なるため、慎重に判断する必要があります。
相続税には非課税枠がある
相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があり、一定額までの財産には相続税がかかりません。
非課税枠は以下の計算式で求められます。
非課税枠 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の人数)
たとえば、法定相続人が1人であれば3,600万円、2人なら4,200万円、3人であれば4,800万円までが非課税となり、相続税は発生しません。
また、配偶者には特別な「配偶者控除」があり、遺産分割または遺贈によって取得した財産のうち、1億6,000万円まで、もしくは法定相続分までの金額については相続税が課されません。
このほかにも、相続に関する控除制度はいくつかありますが、計算が複雑なものも多いため、詳細については税理士や弁護士に相談することをおすすめします。
おわりに
遺産の大部分が不動産で現金が少ないような場合には、相続税をすぐに支払うのが難しくなることがあります。
相続税の納付が遅れると、無申告加算税や延滞税などのペナルティが加わり、負担が増えるおそれがあります。
納税が困難なときには、延納や物納の制度、不動産の売却、借入れ、相続放棄といった対処方法を検討することが重要です。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。