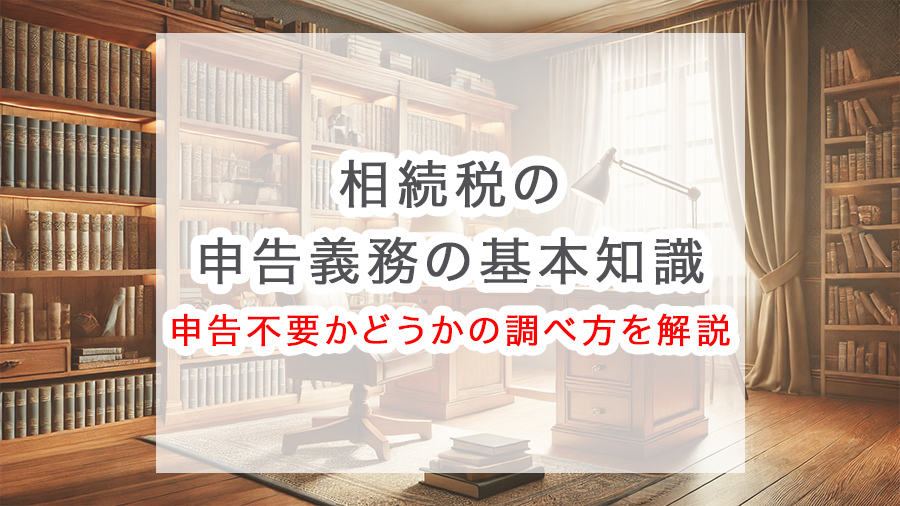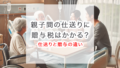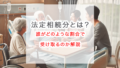相続税の申告義務とは?
相続人が亡くなった方の遺産を引き継ぐ場合、相続税の申告が必要かどうかが問題になります。相続税は、遺産の総額が一定額を超えた場合に課せられる税金です。そのため、全員に相続税の申告義務があるのではなく、申告義務がない相続人もいます。
ただし、税務署から自動的に通知が来るわけではないため、「自分で相続税の申告義務があるか」を確認する必要があります。
相続が発生したら、まずは自分に相続税の申告義務があるか、以下の通り確認していきましょう。
「相続についてのお尋ね」とは?
相続税は自己申告制です。そのため、「申告しなくても大丈夫では?」と思う人もいるかもしれません。しかし、放置しても相続税の支払い義務を免れることはできません。
税務署は被相続人の財産をある程度把握しています。「相続税が発生する可能性がある」と判断された場合、税務署から「相続についてのお尋ね」という書類が相続人に送られてきます。これは、相続開始からおよそ半年ほど経過した頃に送られることが多いです。
この「相続についてのお尋ね」は、遺産の内容を確認し、相続税の申告が必要かどうかを相続人自身で確認し、注意を促すための書類です。もし既に相続税の申告手続きを進めている場合は、この書類に回答する必要はなく、そのまま申告期限内に手続きを進めれば問題ありません。
一方で、相続税がかからない場合でも、税務署に対してその旨を回答しておくことが推奨されます。後から追加の財産が見つかり申告が必要になることもあるため、その時点で財産を把握していなかった証拠として有効になります。
なお、意図的な虚偽とみなされた場合には、重いペナルティである重加算税が課される可能性があるのでご注意ください。
国税庁の「国税庁 相続税の申告要否判定コーナー」はこちら
相続税の申告義務がある人
相続税の申告義務がある「一定の金額以上」とは、具体的にどれくらいの額なのでしょうか?相続税には「基礎控除」という非課税枠が設けられています。遺産の相続税評価額の合計が、この基礎控除額を超える場合にのみ、相続税の申告義務が生じます。
基礎控除額は以下の式で計算されます。
【 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 = 基礎控除額 】
法定相続人とは、民法で定められた相続人を指し、亡くなった方(被相続人)の配偶者や子どもが該当します。例えば、相続人が配偶者と子ども1人の場合、基礎控除額は次の通りです。
【 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円 】
このケースで財産評価額の合計が4,200万円を超えると、相続税の申告義務が発生します。
そうぞくんでは相続税のシミュレーションも可能です。是非ご利用ください。

相続税の申告義務がない人
相続税の申告義務がないのは、相続財産の評価額合計が基礎控除額を下回る場合です。
また、相続財産が基礎控除額を超えていても、申告が不要なケースも存在します。例えば、相続人が障害者の場合に適用される「障害者控除」や、未成年者に適用される「未成年者控除」は、相続税額から直接控除されます。この控除額が相続税額を上回れば、相続税の支払い義務がなくなり、申告も不要となります。
ただし、これらの控除が適用されるのは、相続人全員が該当する場合に限りますので注意が必要です。
基礎控除額以下の場合
相続財産の評価額合計が基礎控除額を下回る場合、相続税の申告義務はありません。
以下の表を参考にしてください。
| 法定相続人 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
このように、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額が大きくなり、申告義務が発生しにくくなります。
相続税の申告で勘違いしやすいケース
相続税にはさまざまな特例があり、それらを活用することで、相続税の支払いを免れることができる場合があります。しかし、特例を適用しても、申告そのものは必要です。
ここでは、相続税の申告手続きで特に注意が必要な2つのケースを紹介します。
1.「小規模宅地等の特例」が適用された場合
2.「配偶者の税額の軽減」が適用された場合
1.小規模宅地等の特例が適用されたケース
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が居住用や事業用として使用していた土地の評価額を最大80%まで減額できる特例です。
例えば、相続した土地の評価額が5,000万円だとしても、この特例を適用すれば80%の減額により1,000万円に評価額が下がります(要件を満たした場合)。その結果、相続財産全体の評価額が基礎控除額を下回ることがあり、この場合には相続税の支払いが不要となります。
ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告が条件となるため、申告義務が発生します。
2.配偶者の税額の軽減が適用されたケース
「配偶者の税額の軽減」とは、被相続人の配偶者が相続した財産に対して適用される特例です。この特例により、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。
例えば、相続人が配偶者のみで、配偶者が1億円の財産を相続した場合、基礎控除額を超えているため通常は相続税が課されます。しかし、この特例を適用すれば、相続財産の評価額が1億6,000万円未満のため、相続税の支払いは不要となります。
ただし、この特例を適用するためには、相続税の申告が条件ですので、申告義務が発生します。
相続税の申告期限は相続発生から10か月以内
「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に、相続税の申告と納付を完了させなければなりません。この期限を過ぎると、附帯税(期限までに申告や納付を行わなかった場合のペナルティ)が加算されるだけでなく、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」などの有利な特例を適用できなくなってしまいます。
相続税の申告義務があることが確認できたら、速やかに申告手続きを開始し、期限内に手続きを完了することが重要です。
おわりに:相続税の申告義務の判断は簡単!ただし、納税が0円でも控除を受けるためには申告が必要なものもある!
相続税の申告は自己申告制で、相続財産が基礎控除額を超える場合のみ申告義務が生じます。
相続税の申告義務があるかどうかは、相続した財産の評価額と基礎控除額を比較することで簡単に判断できます。申告漏れや虚偽申告の場合、ペナルティが科される可能性があるので注意してください。
特に、控除を活用することで納税額が0円の場合でも、申告が条件になっているものもあるのでご注意ください。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税の申告で、もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。