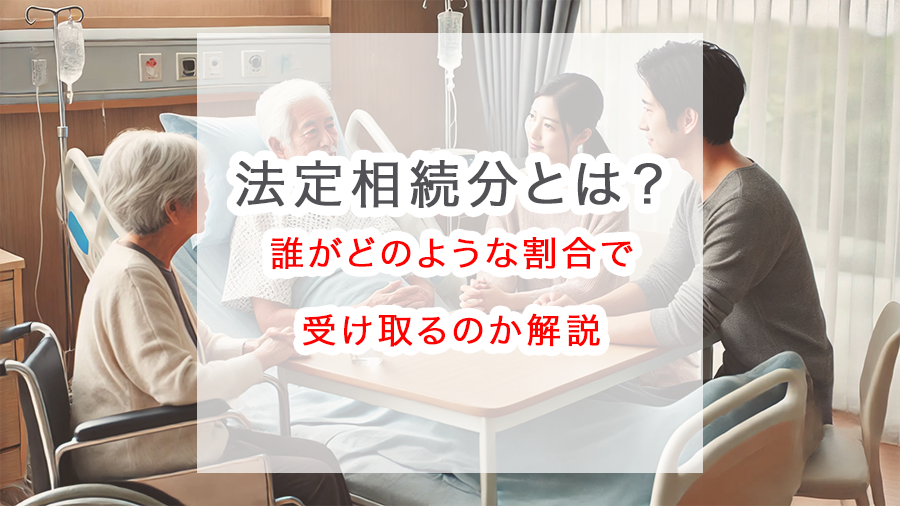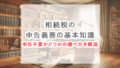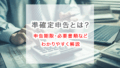相続が発生して遺産分割をする場合や遺言で誰にどのような財産を割り振るかを考えるときに、相続人にどれだけの相続分があるかを知っておく必要があります。
この記事では法定相続分とは何か?誰にどれだけ振り分けられるのか?についてお伝えします。
法定相続分とは
法定相続分とは、相続をする場合に相続人各人の取り分として法律で定められた取り分のことをいいます。
相続が発生した場合、遺言書で誰がどのような財産を取得するか決まっていない場合には、民法に定められている割合に従って相続をすることになります。
この割当てられる割合のことを法定相続分と呼んでいます。
法定相続分と遺留分の関係
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている権利のことをいい、法定相続分の1/2(相続人が直系尊属のみである場合には1/3)で計算されます。
法定相続分がどれだけあるかは遺留分の額に影響するので、遺言や生前贈与をするときに、遺留分を侵害しないように計算する前提として、法定相続分の計算をする必要があります。
遺言がある場合には遺言が優先する
なお、法定相続分に関する規定は、遺言がない場合の規定で、遺言がある場合には遺言が優先します。
なお、遺言ですべての財産についての記載がなかった場合には、遺言の対象になっていない財産については、法定相続分に基づく遺産分割をします。
(参考)一応の相続分とは?
おなじく相続分という言葉を使う用語として「一応の相続分」という用語があります。
一応の相続分とは、法定相続分から特別受益に該当するものを加算し、寄与分に該当するものを除いた相続分を指します。
同じ相続人でも、住宅取得資金や結婚資金を親からもらっていた場合に、相続分で同等の相続を主張するのは不公平といえます。また、被相続人の介護を無償で行っていた相続人が、相続で何も配慮してもらえないのも不公平といえます。
これらの調整をするのが特別受益・寄与分という制度で、法定相続分の計算をした後にこれらで差し引きの計算を行います。
その計算の結果の相続分のことを「一応の相続分」と呼んでいます。
(参考)具体的相続分とは?
相続についての情報を探していると、「具体的相続分」という言葉も出てきます。
具体的相続分とは、一応の相続分をもとに遺産分割をして具体的に受け取ると決まった相続分のことをいいます。
例えば、遺産総額が1,000万円だとして、配偶者と子が相続人である場合、それぞれの法定相続分は1/2で500万円が法定相続分となります。
二人で話し合った結果、600万円相当の不動産と400万円相当のその他の財産で分ける場合には、それぞれ相続することになったもののことを具体的相続分と呼んでいます。
法定相続分のルール
それでは、法定相続分として、誰にどのように割り振られるかの法律でどのように定められているか確認しましょう。
同じ地位の相続人が複数いる場合は頭数で等分する
同じ地位の相続人が複数いる場合は、頭数で等分します。
例えば、子が3人いる場合、相続分は1/3ずつです。
配偶者と共同相続する場合
配偶者と共同相続する場合には、相続の順位によって法定相続分は次の割合で計算されます。
第一順位:配偶者1/2・子1/2
第二順位:配偶者2/3・直系尊属1/3
第三順位:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合は、この割合を頭数で割ることになります。
配偶者と子3人で相続をする場合の法定相続分は、配偶者1/2・子がそれぞれ1/6づつとなります。
なお、そうぞくんでは自動で法定相続割合の金額を算出し、簡単に分割が可能です。
法定相続分にもとづいて遺産分割をする
法定相続分にもとづいて遺産分割を行います。
法定相続分どおり、きっちりに遺産分割をする必要はない
法定相続分の規定はありますが、法定相続分通り1円まできっちり相続をしなければならないというわけではありません。
例えば、遺産が3,000万円であるとして、相続人が2人である場合に1,500万円づつきっちり分けられていない場合でも、遺産分割は有効です。
つまり、長男が遺産のうち1,600万円分を、長女が遺産のうち1,400万円分を相続するという遺産分割をした場合には、それは有効です。
法定相続分と大きな差があっても遺産分割は有効
では、法定相続分と大きな乖離があっても遺産分割は有効なのでしょうか?
例えば、上記の例で、長男が自宅と預金の両方を相続し、長女は自動車のみを相続する、という合意はできるのでしょうか。
この点、法定相続分の規定は、当事者が相続する権利の目安を規定しているものにすぎず、当事者で合意ができているならば、法定相続分からは大きな差があっても、遺産分割協議は有効です。
遺産分割調停・審判では法定相続分に沿った結論になる
もし当事者が遺産分割協議で合意できなかった場合には、遺産分割調停・審判が行われます。
この調停・審判では、法定相続分に沿った形で進むことになります。
まとめ
遺言がない場合には法定相続分に従って相続しますが、これから遺言を作成する場合には遺留分の侵害をしないように、遺留分の計算をする前提として、法定相続分の計算を行うことになります。
法定相続分がどれくらいになるのかわからない場合には、専門家に相談してみてください。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
相続税について、もし不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。