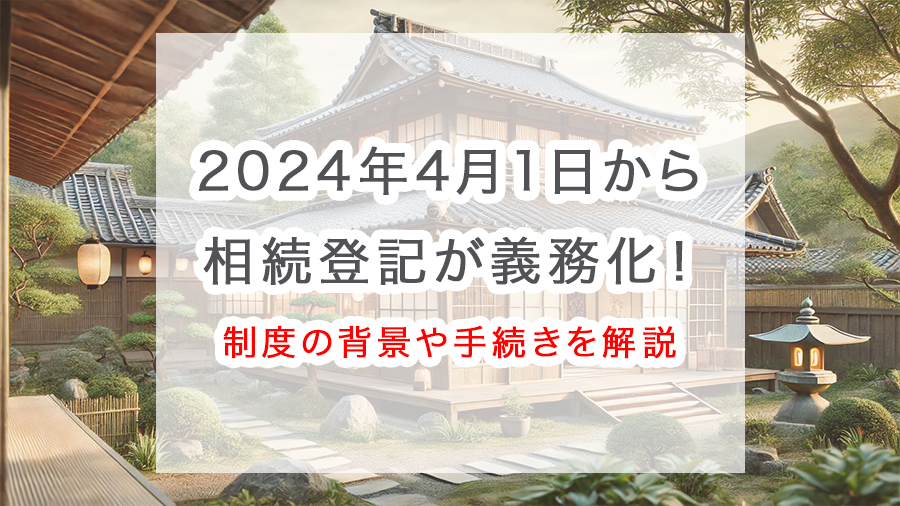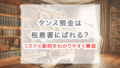2024年4月1日から相続登記が義務化されました。しかし、具体的な内容が分からず、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の義務化に至った経緯や法改正による変更点、手続きを怠った場合のリスクについて解説します。また、相続登記の流れや必要な費用についても詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から相続した不動産の名義を変更する手続きのことです。不動産の所有者は法務省の登記簿で管理されており、相続登記は法務局で行います。
相続登記を適切に行わないと、第三者に対して土地や建物の所有権を主張できません。登記簿の情報は、不動産を売却・活用・担保設定する際にも必要となるため、適正な手続きが求められます。
これまで、相続登記の申請期限は法律で定められていませんでした。しかし、2024年4月1日から相続登記の義務化が決まり、期限内に手続きを行わない場合はペナルティが科されることとなりました。
相続登記が義務化された理由
相続登記が行われないまま所有者が不明の空き家や空き地が増えると、不動産の適切な管理や処分が難しくなります。その結果、不動産取引の停滞や都市開発の妨げとなり、社会問題へと発展しています。こうした状況を改善するため、不動産の所有者を明確にする目的で相続登記の義務化が決定されました。
国土交通省の2016年の調査によると、不動産登記簿で所有者の所在が確認できない土地は全体の20.1%にも及ぶとされています。そのうち67%が相続登記の未実施によるものです。
こうした土地を国や自治体が活用しようとすると、所有者の特定や相続人全員の合意形成に膨大な時間とコストがかかることも問題となっています。
相続登記をしない要因の1つに、所有者側のデメリットが少ないことがあります。相続登記の手続きは複雑であり、専門知識が必要なため、相続人自身が対応するのは容易ではありません。また、相続登記を行うことで固定資産税の支払い義務が発生するため、課税を避ける目的で登記を先延ばしにするケースも見られます。こうした問題を解消するため、相続登記の義務化に踏み切ったと考えられます。
相続登記の義務化はいつから?
相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されます。これにより、不動産を相続した場合は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記を行うことが義務付けられました。
ただし、被相続人が不動産を所有していたことを知らなかった期間は、この3年の期限に含まれません。
また、相続人が複数いる場合は、もっとも遅く相続の発生を知った相続人が認知した日から3年以内に登記を完了させる必要があります。
そのため、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合は、その分割が確定した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。
相続登記の義務化により何が変わるのか?
相続登記が義務化されることで、定められた期間内に登記を行わなかった場合や、氏名・住所変更の手続きを怠った場合に罰則が適用される可能性があります。
相続登記の義務化による罰則
相続により取得した不動産について、正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、本改正では「住所変更登記の義務化」も導入されました。これにより、不動産所有者が氏名や住所を変更した場合、2年以内に登記を行わなければなりません。手続きを怠った場合、5万円以下の過料を請求される可能性があります。
施行前の相続にも適用されるのか?
相続登記の義務化は、施行前に発生した相続にも適用されます。過去に相続した不動産で登記が完了していない場合、2024年4月1日の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
また、法改正前に相続人になっていたものの、改正後になって初めて相続の事実を認識した場合は、認知した日から3年以内に登記を行わなければなりません。
さらに、氏名や住所の変更手続きについても、改正法の施行日から2年以内に行う必要があります。
相続登記で困ったときの新制度「相続人申告登記」
不動産の遺産分割協議が長引くことは珍しくありません。そのため、定められた期限内に相続登記を完了できない可能性もあります。通常、話し合いの途中でも法定相続分に基づいた登記を行うことは可能ですが、必要な資料が多く、手続きが複雑であるため、二度手間になるケースもあります。
こうした状況に対応するため、新たに設けられた制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記は、相続登記の義務を簡単に履行できるようにするための新制度です。この制度では、相続人が次の2点を登記官に申し出ることで、登記簿に記録されます。
- 所有者が死亡し、相続が発生したこと
- 自身がその不動産の相続人であること
この申告を行うことで、相続登記の義務を果たしたとみなされ、期限内に登記しなかった場合の罰則を回避することができます。
相続人申告登記のメリット
相続人申告登記には、以下のメリットがあります。
- 期限内に申請すれば、相続登記の義務を履行したとみなされる
- 相続人が複数いても、単独で申請できる
- 申請に必要な書類が少なく、手続きが簡単
通常の相続登記では、相続人全員の合意が必要ですが、相続人申告登記は単独で申請が可能です。また、申請に必要な書類は亡くなった所有者と申請者の関係が分かる戸籍謄本のみで済むため、手続きの負担が軽減されます。
相続人申告登記の注意点
ただし、この制度は「相続人が誰であるかを証明するだけのもの」であり、不動産の正式な名義変更にはならないため注意が必要です。
相続人申告登記を行ったまま放置すると、後述する「登記しない場合のリスク」が発生する可能性があります。そのため、最終的には正式な相続登記を行う必要があることを忘れないようにしましょう。
不要な土地を国に返せる「相続土地国庫帰属制度」
「相続した土地を利用する予定がなく、そのまま放置している」というケースは少なくありません。こうした状況に対応するため、「相続土地国庫帰属制度」が新たに導入されました。これにより、不要な土地を国に返すことが可能になります。
ただし、この制度を利用すれば無条件で土地を放棄できるわけではありません。申請には審査があり、さらに管理コストを基に計算された10年分の負担金を支払う必要があります。また、すべての土地が対象となるわけではなく、申請が認められないケースもあるため、事前に十分な確認が必要です。
国に返せる土地の条件
次のような土地は、国庫帰属の対象外となります。
- 建物が建っている土地
- 土壌汚染がある土地
- 担保権が設定されている土地
- 他人が通路として使用している土地
- 権利争いが発生している土地
これらの条件に該当しない場合に限り、申請が可能となります。
制度の開始時期
相続土地国庫帰属制度は、相続登記の義務化に先行して2023年4月27日から施行されています。相続した土地の管理が難しい場合は、この制度の利用を検討するとよいでしょう。
相続登記の手続き
相続登記の申請は、相続する不動産を管轄する法務局で行います。手続きの大まかな流れは以下のとおりです。
- 相続する不動産を確認する
- 遺言または遺産分割協議で不動産を引き継ぐ相続人を決定する
- 必要な書類を収集・作成する
- 管轄の法務局へ申請する
登記の申請では、登記事項証明書に必要事項を記入し、登録免許税分の収入印紙を貼付したうえで、必要書類とともに法務局の窓口または郵送で提出します。申請後、登記が完了していることを確認すれば手続きは終了です。
なお、遺産分割による登記と遺言書による登記では、必要な添付書類が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
相続登記は専門家に依頼すべきか?
相続人が1人または配偶者と子どもだけといった比較的シンプルなケースでは、自分で相続登記の手続きを行うことも可能です。特に、平日に役所へ行く時間が確保できる場合は、専門家に依頼せずに進めることも考えられます。
しかし、不動産の権利関係が複雑な場合や、急いで不動産を売却したい場合は、専門家(司法書士など)に依頼したほうがスムーズに進められるでしょう。
相続登記にかかる費用
相続登記に必要な費用は、以下の2つです。
登録免許税
・不動産の固定資産評価額の0.4%を納税
・収入印紙は法務局または郵便局で購入可能
必要書類の取得費用
・戸籍謄本(1通あたり500〜700円)
・登記事項証明書(1物件あたり600円)
・印鑑登録証明書(1通あたり500円)
・住民票などの証明書類
一般的に、総額2〜3万円程度になることが多いです。
また、司法書士に依頼する場合は手数料として3〜10万円程度がかかります。手続きをスムーズに進めるために、時間と労力を考慮して専門家へ依頼するかを検討するとよいでしょう。
まとめ:相続登記は期限内に必ず完了させよう
相続登記の義務化により、期限内に登記を行わなかった場合には罰則が適用される可能性があります。そのため、相続が発生した際は、速やかに必要な手続きを進めることが重要です。
相続登記の手続きに不安がある場合は、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。適切な対応を行い、トラブルを避けるためにも、早めの準備を心がけましょう。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし相続登記に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から司法書士など専門家にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。