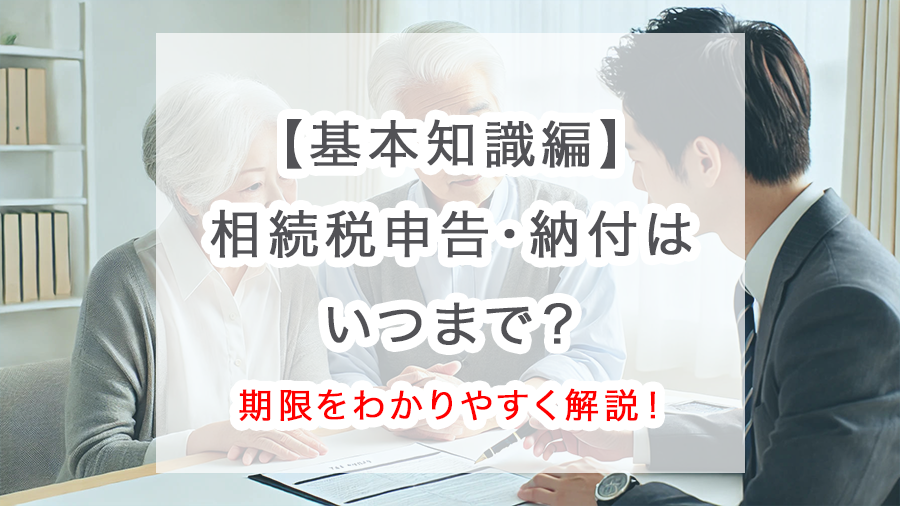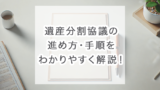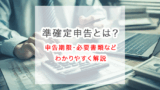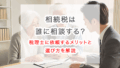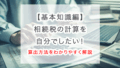大切なご家族が亡くなった際、相続財産の金額によっては、相続人が相続税を支払う必要がある場合があります。その場合、税務署へ相続税の申告を行い、期限内に納付をしなければいけません。
相続税の申告と納付には、明確な期限「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」が設けられています。この期限を過ぎると、延滞税や加算税といった附帯税が課されることがあります。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、期限の延長が認められることもあります。
この記事では、相続税の申告期限および納付期限、そしてその起算点となる相続開始日についても詳しく解説しています。
相続税の申告期限と納付期限
相続税には「申告期限」と「納付期限」が設けられており、いずれも厳密に定められています。
申告とは、税務署に相続税申告書と関連書類を提出し、納める税額を報告することです。納付は、その申告に基づいて税金を支払う行為を指します。相続税の納付は、原則として現金による一括払いとなっています。
これらの期限は、どちらも「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」とされています。たとえば、被相続人が1月15日に亡くなった場合、その年の11月15日が申告と納付の期限です(土日祝日に当たる場合は翌営業日)。
多くの場合、申告を済ませた後に納付を行いますが、同時に行っても問題ありません。
なお、「相続開始日」とは、被相続人が亡くなった日のことです。相続は死亡の瞬間から発生しますが、申告・納付期限の起算点は「亡くなったことを知った日の翌日」とされており、これは行方不明や災害などにより死亡日がすぐに確認できないケースを考慮して定められています。
相続税の申告と納付までの流れを確認
相続が発生してから、相続税の申告・納付を行うまでの一般的な流れは、以下のとおりです。
被相続人の死亡日
この日が相続の開始日となります。「相続発生日」または「相続開始日」とも呼ばれ、すべての相続手続きはここから始まります。
相続人と遺言の有無の確認
誰が財産を受け取るかを確認します。法定相続人だけでなく、遺言書によって財産を取得する人(受遺者)が指定されている場合もあります。遺言書があるかどうかもこの段階で確認します。
財産と債務の確認
被相続人が残した財産と債務(借金など)を調査します。相続ではプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ必要があります。財産の内容によっては相続税が発生しないこともあります。
遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で財産の分け方を話し合います。民法では法定相続分が定められていますが、相続人同士の合意があれば、異なる分け方でも問題ありません。
相続放棄または限定承認の申述
相続を放棄する場合や、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法)を選ぶ場合は、3か月以内に家庭裁判所へ申述します。
準確定申告
被相続人が亡くなった年に収入があった場合は、相続人が代わりに確定申告を行います。これを「準確定申告」といい、期限は死亡日から4か月以内です。
相続税の申告と納付
申告に必要な書類をそろえ、税務署に提出します。相続税の納付もあわせて行いましょう。期限はいずれも、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続の事情は人それぞれで、すべてがこの手順どおりに進むとは限りません。しかし、申告と納付の期限は原則として延ばせないため、できるだけ早めに準備や話し合いを進めることが大切です。
申告や納付が遅れた場合
相続税の申告や納付を期限内に行わなかった場合、ペナルティとして罰金が課されます。代表的なものは以下の3つです。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
これらは本来納めるべき税金に加えて追加で支払うことになるため、申告・納付は期限を守って行うことが重要です。
申告や納付の期限に間に合わない場合の対応
相続税の申告と納付には厳格な期限が設けられていますが、状況によっては「間に合わない」というケースも考えられます。そのような場合の対処法として、まずは期限内に可能な範囲で申告と納税を行い、その後に払いすぎた税金について還付を申請する方法があります。
また、正当な事情がある場合には、申告や納付の期限が延長されることもあります。期限に間に合わない可能性があると感じた時は、早めに対応を検討することが大切です。
申告期限に間に合わないときの対応策
申告期限に遅れる主な原因は、遺産分割協議がまとまらないことにあります。いわゆる「相続争い」により申告が間に合わず、無申告加算税などのペナルティを受けるケースも少なくありません。
このような場合には、まず法定相続分で申告と納付を行い、その後、分割内容が決定した段階で「更正の請求」により過払い分の税金を還付してもらう方法があります。
あわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割が完了した際に「小規模宅地等の特例」なども適用可能になります。
参考サイト:国税庁ページ
納付期限に間に合わないときの対応策
納付が間に合わない理由としてよくあるのが「手元に現金がない」ケースです。相続税は原則として現金による一括納付が求められるため、財産の多くが不動産である場合などはすぐに現金を用意できないことがあります。
このようなときには「延納」という制度を活用することが可能です。延納とは、相続税を分割で毎年支払っていく制度で、利子税は発生しますが、納付の負担を軽減できます。
延納を利用するには、次の4つの条件を満たす必要があります。
- 金銭による一括納付が困難であること
- 相続税の金額が10万円を超えていること
- 申告期限までに延納申請書、担保に関する書類、納付困難の理由書を提出していること
- 延納税額に見合う担保を提供できること
なお、延納による支払いも難しい場合には、不動産や株式などの「現物」による納付(物納)を選択することも可能です。
申告期限の延長が認められる主なケース
申告期限の延長が認められる代表的なケースは次のとおりです。
災害などにより申告が困難な場合
地震、台風、大雨、新型コロナウイルス感染症などの災害・事故によって申告が困難な状況であれば延長が認められます。
相続人に異動があった場合
認知や相続人の廃除などにより、相続人の構成に変化が生じたときは延長の対象となります。
遺留分侵害の請求があった場合
遺言などによって遺留分を侵害された法定相続人が金銭の支払いを求め、調整が必要になった場合です。
遺贈に関する遺言書が後から見つかった場合
新たに遺言書が発見され、内容の再計算が必要になったときも延長が認められます。
胎児が出生した場合
民法では胎児も相続人として扱われますが、相続税法上では出生後に課税関係が確定します。出生していない場合は本来の申告期限までに申告をしなければなりません。しかし、仮に胎児が出生したものとしたら、相続税の申告書を提出する義務がなくなる場合、胎児が生まれてから2か月の範囲内で延長が可能です。
延長が可能な期間
いずれも延長期間は2か月とされています。ただし、災害などによるケースでは「その事情が解消された日から2か月以内」が延長期間となります。
延長を希望する場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。この書類は国税庁のホームページから入手可能です。
申告期限の延長が認められた場合、その申告書を提出した日が納付の期限になります。別の日に納付した場合は、延滞税が課せられることがあるため注意が必要です。
おわりに:相続税の申告と納付はなるべく早めに!
相続税には、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」という明確な申告・納付期限が定められています。この期限を過ぎると、追加の税金(追徴課税)が課されるだけでなく、「小規模宅地等の特例」などの有利な制度も適用できなくなる可能性があります。
10か月という期間は一見長く感じられますが、財産の確認、遺産分割協議、必要書類の準備などに時間を要するため、あっという間に期限が迫ってしまうこともあります。ただし、やむを得ない事情がある場合には、申告・納付の期限延長も検討すると良いでしょう。
そうぞくんは、相続税の申告書を簡単に作成することができるWEBサービスです。
もし相続税に関して不安なことや疑問などございましたら、サイト内から専門家(税理士、弁護士、不動産鑑定士など)にご相談いただくことが可能です。
是非、ご利用ください。